
第27回ICOMドバイ大会2025 開催報告:博物館分野の新たな戦略・方向性を提示
2025年11月11〜17日にアラブ首長国連邦ドバイで開催されたICOM(国際博物館会議)第27回総会は、「急速に変化するコミュニテ…
- Museums have no borders,
they have a network. - ICOM(国際博物館会議)日本委員会は、世界の博物館の進歩発展に貢献すると共に、日本国内におけるICOM会員の活動をサポートする事業を展開しています。博物館の国際的なコミュニティに参加してみませんか?
- ICOM Kyoto 2019
- 25th ICOM
General Conference

NCCPP & ICMS ロサンゼルス大会2024記録集を公開しました
[2026.1.29]
国際委員会の一つであるICOM-ICMS(International Committee for Museum Security・博物館セキュリティ国際委員会)は、National Conference…

【2/7開催】ウポポイで国際シンポジウム「先住民族×博物館」
ICOM団体会員である国立アイヌ民族博物館は、2026年2月7日(土)、8日(日)に国際シンポジウム「『先住民族×博物館』―協働・対話・更新―」を開催します。このシンポジウムでは、アメリカ、オーストラリア、フィンランド、日本という世界各地に…
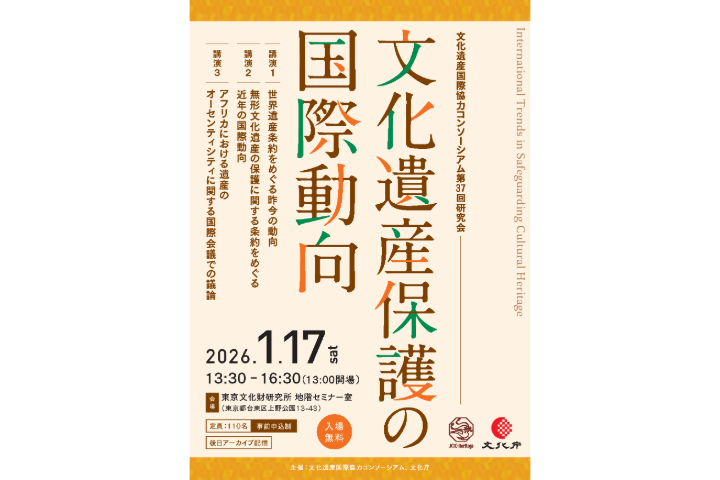
【1/17開催】 文化遺産国際協力コンソーシアム 第37回研究会「文化遺産保護の国際動向」
[2025.12.16]
⽂化遺産国際協⼒コンソーシアムが主催する研究会「文化遺産保護の国際動向」についてのご案内です。
7月中旬にユネスコ本部で行われた第47回世界遺産委員会の様子や、インド・デリーで12月に…

[2025.10.1] 原文はこちら
25周年を迎えるレッドリストを次世代へ
ICOMは、文化遺産の違法流通を防ぐためのツールである ICOMレッドリスト(Red Lists)を対象とした調査を開始しました。これは、レッドリス…

【10/7開催】特別講演会「変わりゆく博物館-オランダの挑戦」
[2025.9.18]
ICOM日本委員会が共催する講演会「変わりゆく博物館-オランダの挑戦」が10月7日(火)に国立科学博物館にて開催されます。
今日の博物館を取り巻く国際状況は、文化的多様性の尊重、相互理…
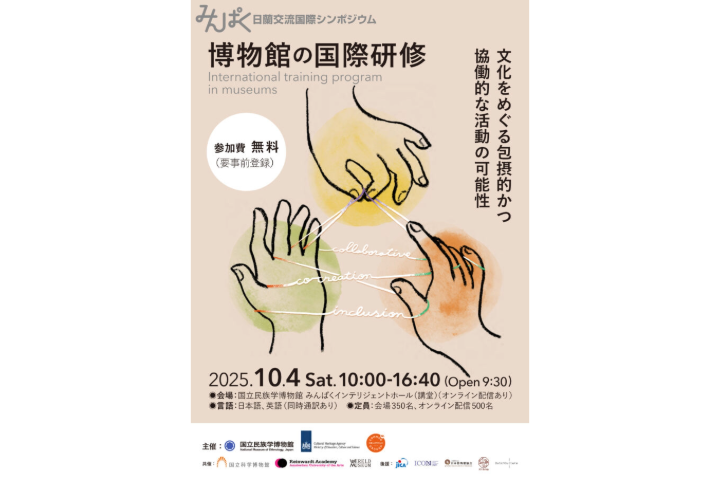
[2025.8.21]
ICOM日本委員会が後援する日蘭交流国際シンポジウム「博物館の国際研修 ―文化をめぐる包摂的かつ協働的な活動の可能性」」が10月4日(土)国立民族学博物館で開催されます。
人類共通の財…

【8/16開催】 ICOM日本委員会共催シンポジウム「紛争下の被災文化遺産と博物館の保護―スーダン共和国の事例から―」
[2025.8.4]
ICOM日本委員会が共催するシンポジウム「紛争下の被災文化遺産と博物館の保護―スーダン共和国の事例から―」についてのご案内です。
2023 年に始まった軍事衝突により、スーダンの文化遺産お…

本年度の文化庁事業「令和7年度博物館職員等在外派遣事業」について、博物館に関する国際会議等への参加や博物館や関係団体での調査・研究、現地視察のために海外への派遣を希望される方を募集しています。
【募集概要】…

ウクライナの博物館と文化遺産の保全・復旧に引き続きご支援ください
[2025.5.26] ICOM日本委員会では、ロシアのウクライナ侵攻により被害を受けた博物館や文化遺産の保全・復旧のための寄附金の…
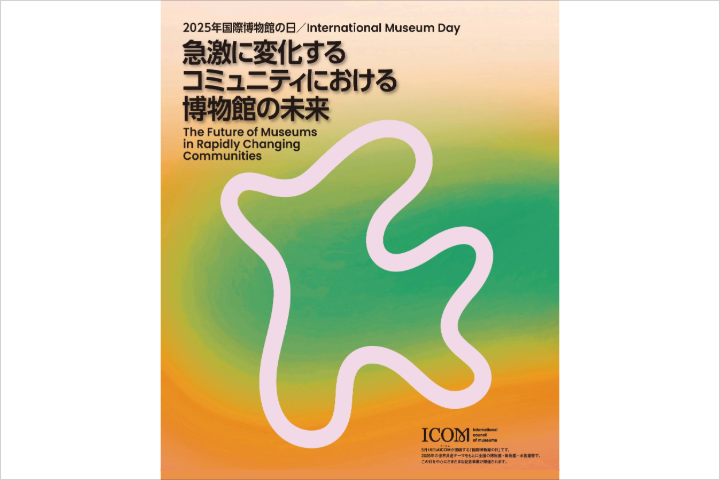
【5/18開催】国際博物館の日シンポジウム 東京国立博物館にて開催
[2025.4.23]
2025年の国際博物館の日のテーマは、“The Future of Museums in Rapidly Changing Communities(急激に変化するコミュニティにおける博物館の未来)”です…

【動画公開】令和6年度在外派遣事業 成果報告会「国際ネットワーク構築・国際プレゼンス向上を目指して」
令和6年度在外派遣事業 成果報告会「国際ネットワーク構築・国際プレゼンス向上を目指して」が3月3日にオンラインにて開催されました。本年度は、8名の方々が当文化庁事業を活用し、海外の国際会議や博物館等に派遣されました。派遣者の得た成果をみなさ…
