
June 17, 2022
代替できない固有の価値をいかに生み出すのか―パンデミックの中での浜松科学館の取り組み
藤江 亮介
浜松科学館
2020年、日本国内でもCovid-19の感染が拡大し、大半のミュージアムが一定期間の臨時休館を余儀なくされた。当時筆者が在籍していた浜松科学館では、同年3月から5月にかけて約3か月間臨時休館となったが、各館のおかれている状況によっては、さらに長い期間に及んだ例もあるだろう。そのあと再開して開館できていても、感染拡大の波が大きくなるたびに、利用者数は落ち込むということが繰り返されてきた。
ミュージアムが利用者や市民に対して価値を提供するにあたり、来館してもらうというチャネルが一時的に閉じてしまったこと、そして縮小してしまったことのインパクトは大きい。浜松科学館のような地方都市の科学館では、調査・研究や収集・保存といった機能は限定的であり、展示や催しによる教育普及活動に運営の重心が置かれているため、あくまでも利用者が集い、そこで事物に触れ、交流や体験が充実することで施設の価値が高まる。しかしパンデミックの中では、いわゆる三つの“密”を回避せねばならないという環境面での制約を抱え、自らの存在意義を問われるような状況に直面したわけだ。
多くの館が対応策として取り組んだのはオンラインコンテンツの制作である。日ごろ展開しているプログラムを動画や記事などにまとめ直し、それをオンラインで公開することで、来館してもらうというチャネルに代わる新たな接点をつくり、そこで価値創出しようする試みだといえる。

浜松科学館でも、通常館内で行っている実験や工作などの体験プログラムを自宅で楽しんでもらうことを狙い、上記の臨時休館中に、「おうちDEみらいーら」と題した1本5分ほどの動画を約80本公開した。ただその一方で、それらの企画を担当した職員達には違和感も生じていた。実験や工作に関する情報はインターネット上に溢れており、検索すれば類似したものに数多く行き当たるし、やはりオンラインでの視聴は来館して体験することの代わりにはならないからである。
ここで、臨時休館中に公開した約80本の動画について、2020年6月~2021年5月の1年間での視聴状況に着目してみたい。視聴回数の上位3件のうち、1位はシャボン玉液の作り方を紹介したもの、3位は牛乳パックでブーメランを作る方法を紹介したものであった。この2つには共通していることがある。それは浜松科学館の定番プログラムとして毎日実施しているサイエンスショーに関連した内容だという点だ。
2019年に全面的に展示更新が行われた際に館内の中央にステージが配置され、その場所で行われるサイエンスショーは来館者の20~30%が観覧する人気コンテンツとなっている。10種類以上ある演目を日替わりで展開しており、ショーで用いている実験道具の作り方を教えてほしいという問い合わせが観覧した方々からたびたび寄せられるのだが、それが当該動画の視聴回数増加につながっているようなのだ。
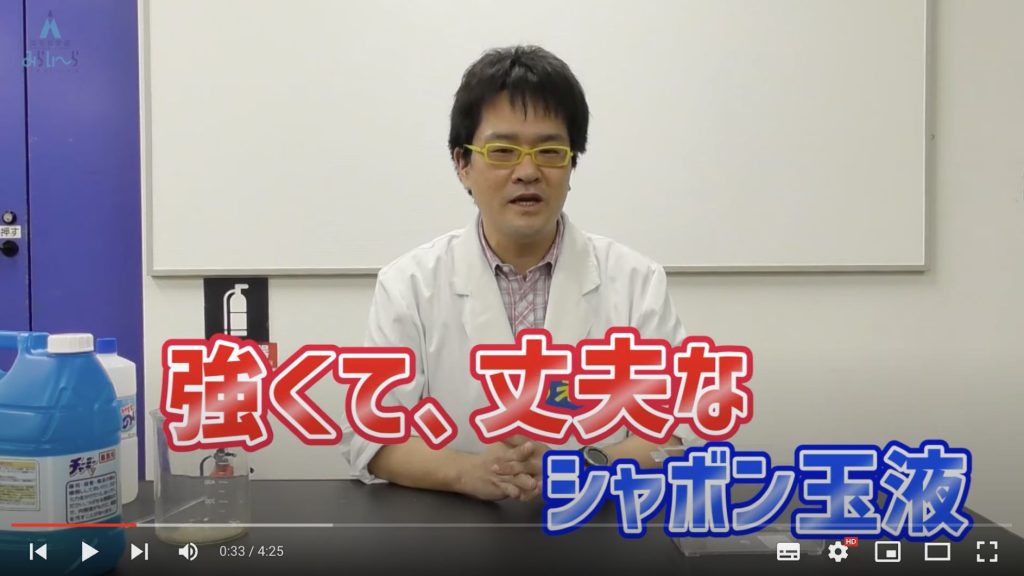
やや冗長的な書き回しになってしまった。筆者がこの出来事から読み取ったのは、施設に利用者が集い、そこでの交流や体験によってしか生まれない固有の価値とはどのようなものかを、パンデミックの最中だからこそ、改めて問い直さなければならないということである。オンラインで公開した動画も、それ単独ではなく、館での体験を拡張するための情報として位置付けることで、固有性が高まることが確認できた。来館というチャネルに代わる接点を増やしていくのではなく、実空間で提供している交流や体験の価値をより高める方向で、パンデミックの中での施策を考える場合に、どのような打ち手が有効なのだろうか。いくつか他の取り組み実例を交えつつ論を進めてみたい。
プラネタリウムで疑似旅行「みらいーら 夜の科学館」
緊急事態宣言の発出やまん延防止等重点措置の適用といった感染拡大防止策に伴い、飲食店への休業または営業時間短縮の要請が繰り返し行われたことは記憶に新しい。ナイトタイムエコノミーが壊滅的な打撃を受けるなか、浜松科学館では毎月第3金曜日に夜間開館する取り組みを2020年の7月から続けてきた。通常17時に閉館となるところを、入場者を高校生以上に限定したうえで、17:01~19:30(8月は18:01~20:30)を臨時開館時間とし、大人向けの特別プログラムを展開している。
この企画の核となったのは、プラネタリウムの特別投映「STAR FLIGHT」だ。月替わりで世界各地の名所を訪れ、現地の夜空と星に関する話を紹介するという内容なのだが、この“疑似的な旅行”が期せずして世の中の需要をくみ取る格好となり、これを目当てに毎月200人以上が来館した。外出することの心理的負荷が高まり、遠くに出かける機会が劇的に少なくなったことが、平常時には発生しないような特需を生み出したとみられる。
ただし、これは半年以上前から準備を進めていた企画で、パンデミックに合わせて発案されたものではない。日ごろ来館する層とは異なる属性の大人の方々が、平日の夜間に科学館に足を運ぶ光景を目の当たりにし、運営に携わる私達自身が潜在的な施設価値を認識させられた。また同時に、特別プログラムに明確な訴求力があったことで、需要がつくり出されたという面もあったといえるだろう。


地域の観光資源のコンテンツ化「天竜浜名湖鉄道星空紀行」
先述した「STAR FLIGHT」と同様、プラネタリウムの空間特性を生かして新たな体験価値を提供した例がある。2020年の10月~11月に浜松科学館で投映したプラネタリウム番組「天竜浜名湖鉄道星空紀行」だ。この番組はコロナ禍で注目されたマイクロツーリズムの考え方をプラネタリウムで体現したような内容になっている。
具体的に言うと、
市街地から30分程度で見に行ける中山間地域での星空
車窓に映る水辺や緑地、文化財などの景色
といった地域の魅力を科学館で再発見してもらおうという趣旨で、臨場感を演出するために、番組制作を担当した職員が360度撮影できるカメラを片手に実際に鉄道に乗り込んで何度も撮影を行った。星空の解説はもとより、ドームシアターに映し出されたそれらの実写映像が大変好評で、その年度に投映した番組の中で1回あたりの平均観覧者数が最も多かったことも特筆に値する。


常設展を活用した新ツールの開発「ヒラメキ ナゾトキ みらいーら」
コロナ禍で各館が苦心したことの一つに、展示解説のような利用者と対面で接するサービスをどう再設計するかが挙げられるだろう。やはり職員の側から積極的に声をかけていくやり方をとりづらい状況が今後も当面続くとみられる。
浜松科学館には約100点の常設展示があり、職員がインタープリテーションすることで展示による学びを深めてもらうというコンセプトで配置されているものが多い。従来のようには声かけすることが難しくなったなかで、常設展エリアでの体験の質を高めるための新たなツールとして開発したのがゲームブック型の冊子である。「ヒラメキ ナゾトキ みらいーら」という名称で、冊子の1ページごとに“謎解き”が設定されており、各設問は常設展示アイテムに紐づけられている。設問に答えていく過程で、展示の内容をよく観察したり、展示アイテムで実験したりしなければならない。
このツールは2020年の7月から12月に運用し、約1500部発行した。ゲームブックそのものの満足度が高かったことに加え、手元にこのツールがあることで利用者の方から職員に話しかける場面が目に見えて増加したほか、普段素通りされてしまうような展示でも興味をもってもらえるなど副次的な効果も確認できた。2021年に入ってから、ゲームブック型のツールの第2弾となる「さがして ためして みらいーら」も運用中で、浜松科学館の楽しみ方のバリエーションとして定着しつつある。


まとめに代えて
2020年から2021年にかけてのいくつかの取り組みを紹介したが、振り返ってみると、ミュージアムでの交流や体験によって生まれる固有の価値を高めるための施策に注力した結果、パンデミックの中でも一定程度の集客を維持できたといえる。
とはいえ、指定管理者としての経営面での状況に言及せずにいるのはいわば“経済なき道徳”を語っているのに等しいだろう。この2年間は利用料金収入の落ち込みが大きかったことは動かしがたい事実であり、設置者(浜松市)からの補填なくしては事業収支がバランスしなかった。感染拡大の影響が徐々に薄まるとすれば、これから利用料金収入を一定の水準に回復させられるかどうかが焦点となる。
浜松科学館では2022年から2024年の3か年の中期計画を策定したばかりだが、その内容は図らずも2019年のICOM京都大会で掲げられた「文化の結節点としてのミュージアム」というテーマに近接したものとなり、計画策定に携わった職員達がそのような領域での活動を自らの使命として捉え始めていることが垣間見られた。先述したプラネタリウム番組制作など、コロナ禍で取り組んできた仕事が個々の意識の変化を生んでいるのかもしれない。地域の文化振興の中核施設として、利用者や市民に対してどのような価値を提供すべきなのか、地方都市のミュージアムが常に自問すべきことであるが、パンデミックの最中でより一層切実にその問いを突き付けられた。
(ふじえ りょうすけ)