
February 8, 2023
民族文化の発信に、「バーチャル」の可能性を拓く
国立アイヌ民族博物館 アソシエイトフェロー
国立民族学博物館 外来研究員
劉高力
筆者は、国立アイヌ民族博物館研究学芸部展示企画室に所属しており、展示の多言語化および展示映像、バーチャル博物館を担当している。本文では、国立アイヌ民族博物館で行なっているバーチャル博物館制作の実例を挙げて、民族学系博物館の展示における「バーチャル」化実践、および「バーチャル」の可能性について展望したい。博物館人の一人として、個人的な経験と思いを述べる。
初心記——突然降りてきた「バーチャル」業務と疑問点
2020年7月、新型コロナウイルスの影響が世界中に拡大している最中に、日本最北の国立博物館「国立アイヌ民族博物館」が開業を迎えた。この博物館は、民族共生象徴空間(愛称がウポポイ)の中核施設であり、民族学を主題にする二番目の国立博物館である。1970年代に大阪で開館し、世界諸地域の民族文化に関する展示・研究を目的にする国立民族学博物館とは異なり、日本の先住民族アイヌの歴史・文化等に関する正しい認識と理解を促進するとともに,新たなアイヌ文化の創造および発展に寄与することを理念とする博物館である。
館の所在地である北海道白老町は昔からアイヌ民族の集落があり、自然が豊かなところである。筆者は通勤途中、毎日のように、アイヌ文化にとって大事な存在であるものに出会う。キタキツネやエゾシカが日々道を走っていて、ヒグマがたまに自宅周辺に出てくる。長年にわたって、アイヌ文化・歴史を研究している同館の研究者にとっては、「フィールドワーク」の調査地に住むような夢みたいな生活と言えば間違いない。一方で、大都市の隅々にまで溶け込んだテクノロジーが、まだこの地には届いていない面もある。たとえば、家庭用WIFIの導入が珍しいため、設置の際に、自宅前の道路が一時的に封鎖され、本格的な工事が行なわれた。職場のエスカレーターが、白老町内の最初のエスカレーターとなり、ある意味で博物館の誇りともなっている。
このような環境の中で、開館10ヶ月後、2021年5月、コロナ禍での「新しい生活様式」に対応したアイヌ文化の情報発信のため、先端VR技術を活用し「バーチャル博物館」を作成する業務が降りかかってきた。検討チームを立ち上げたところ、「バーチャル博物館」とは何か、「どこからスタートすればよいか」、「必要性がどこにあるのか」、「非日常なもの、テクノロジーと自然な民族文化のイメージのズレが大丈夫か」など、学術面、技術面等からさまざまな問題に直面した。当時の基本構想は、国立科学博物館の「かはくVR」を見本にして、ほぼ同じように、在宅でも博物館の雰囲気を体験できるものを作るというものだった。それに従って、3Dカメラを用いて撮影し、デジタルツインの大手会社Matterportの3Dモデリングサービスを利用できる業者を入札で選定し、11月末に、博物館全体の3D撮影が完了した。問題点や時間に追われながらも、ここまでの作業はとりあえず順調に進行していた。
再認識——「バーチャル」とは?
12月初旬、3Dモデル作成と同時に、アイヌ語を含めて、8言語表記で書かれた博物館基本展示室の大中テーマ、説明文コンテンツをまとめ、3Dモデルに差し込む作業する予定であった。しかし、直前になって「バーチャル博物館」とは何かという根本的な疑問が、予測しなかった形で再び浮かんで来た。展示室の解説文のアイヌ語執筆者は、それぞれのアイヌ語方言の専門家であり、博物館へ寄稿した際に、執筆した解説文は国立アイヌ民族博物館の展示室内でのみ使用可能という条件があった。「バーチャル博物館」という、いわば本物の博物館を3Dモデルの形で、だれもがどこでも閲覧可能なインターネットの仮想空間に再現する「展示室」が、「国立アイヌ民族博物館の展示室」といえるのかという疑問が持ち上がった。
そこで、アイヌ語解説文を「バーチャル博物館」でも使用できるように、担当者が執筆者に一人ずつ確認し、2022年2月までに、執筆者全員から承諾を得ることができた。その間に、アイヌ語の担当者が執筆者たちから聞かれたのが、「バーチャル博物館」とは何かという質問であった。
「バーチャル」とは、英語の「Virtual」である。その単語が日本語では、「(表面または名目上はそうでないが)事実上の、実質上の、実際(上)の、虚像の」[i]、「実体・事実ではないが本質を示すもの。仮の、仮想の、虚の、虚像の」[ii]などと訳された。実は抽象的な意味で、指示する範囲が広い。「VR」技術とは、「バーチャルリアリティ」(virtual reality)のことで、仮想の「バーチャル」と現実の「リアリティ」の二項対立を統合する造語である。これはもともと情報工学関連の用語である。日本バーチャルリアリティ学会の定義によると、バーチャルリアリティの特徴は、「人間によって自然な3次元空間を構成しており」、「人間がそのなかで、環境との実時間の相互作用をしながら自由に行動でき」、「その環境と使用している人間とがシームレスになっていて環境に入り込んだ状態がつくられている」、すなわち「3次元の空間性」、「実時間の相互作用性」、「自己投射性」の三要素が基本である。[iii] VRゴーグルをかけて3次元コンテンツを見て、体験することが、現在のVR体験でよくあるパターンである。

「バーチャル」と「バーチャルリアリティ」の定義を比較してみたところ、「バーチャル博物館」の意味はますます曖昧になっていた。おそらく、コロナ禍の緊急対応の一つとして、来館できない人々にも博物館が楽しめるように、Matterportという技術を活用し、博物館そのものをオンラインで「虚像」として公開することを目指していたのだろう。本格的な「バーチャルリアリティ」のように、新しいテクノロジーを利用し、人間と環境の相互作用によって、新しい体験や知識を生み出すまでには、更なる検討が必要になるだろう。
考え直す——道を広く
上述のように、「バーチャル」についてさまざまな思いをクリアしながら、思考がどんどん広がり、「バーチャル博物館」制作に対する認識も一変した。
形としては、実在しないが、本質を表現することが肝心である。Matterportの3Dモデリングで全館の「形」を作り出していたが、その形に限らず、館の理念の伝達、アイヌ文化の発信のため、より多くの人が鑑賞できるように、言語・文化の壁、身体的障害を超えて、包摂的な空間を作ることを目標とすることが重要ではないかと考えはじめた。
このような考えを持ち、オンラインの「視覚」的な体験に注目するだけでなく、「聴覚」にも力を入れることにした。
まず、Matterportの3Dモデリングにはない、ほかのソフトと連動する自動音声解説コースを開発し、バーチャル博物館のページに埋め込んだ。音声の内容は、展示室の概要について、各テーマの展示担当者がその展示の主旨を説明するものである。収蔵品の「医者」であり、常に博物館の展示環境を維持する博物館文化財保存修復の専門家の声も聞かせたい。そのすべての内容を、英語、中国語、韓国語に翻訳、録音し、それぞれの言語のバーチャル博物館ページに導入した。すなわち、アイヌ語を第一言語にして日本語が通用する、現実の形を持つ「国立アイヌ民族博物館」が、オンラインの「バーチャル博物館」で日本語、英語、中国語、韓国語の「虚像」を持つ、4倍の「形」となり、「質」の面でもさらに充実した。

次に、「相互作用」の距離感を考えた。実在の博物館のように、多数の来館者と同時に見学するのとは違い、オンラインバーチャル博物館の「来館者」は一人で見ることが多い。その一人一人に、アイヌ文化のことをうまく伝えられるように、プロのナレーターが話すよりも、その「本質」をよくわかっている研究員、学芸員の口から実際の思いを話せばよい。そのため、国立アイヌ民族博物館のバーチャル博物館の音声は、館長のアイヌ語挨拶を始め、多言語を含めて、すべて博物館職員が出演し、筆者が博物館の音響室で収録・編集したものである。大人も子供もわかりやすく、現実にいる友人が話すような雰囲気を作ることができた。その結果、当初心配していた「派手すぎ」ではないかという心配もなくなっていた。

最後に、バーチャル博物館と、同館のほかのオンライン資源を整合する試みについて述べる。国立アイヌ民族博物館の展示室で展示されたものは、収蔵品のごく一部であり、大量の収蔵品が収蔵庫に保管されている。収蔵品データベースはウェブページからアクセスできるが、利用率が低い。バーチャル博物館では、4つの仮想モニターを設置し、収蔵資料データベースとリンクさせることで、簡単にアクセスできるようになった。

博物館売店で販売しているアイヌ工芸品も、ウェブページからオンラインショップにアクセスすれば入手可能となっていた。それらの機能をわかりやすく利用できるように、バーチャル博物館の空間に、仮想什器をおいてリンクを作成した。さまざまな資源へのツールをまとめ、有効活用を実現させている。

将来の展望——金賞から
以上のように、試行錯誤、ブレインストーミングを重ねて、国立アイヌ民族博物館のバーチャル博物館はギリギリで年度内に完成し、2022年4月22日公開された。
だが、従来から、博物館展示のメインは実物展示、バーチャルも、展示の音響映像も、いずれも実物展示の補足として、副次的に位置づけられている。実物展示のようには重要視されていないということが強く感じられた。いつかオンラインの3Dモデリングの枠から脱出し、マルチメディアと技術を活かして、さまざまな形でオンラインと現実が連動する「バーチャル」の展示会を開くという夢を持っているが、なかなか実現できない。
ほかの国の博物館がどのような展示をしているのか、「バーチャル」と「実物」の間でどのようにバランスを取っているのか、これまでのわれわれの工夫を人に見せたいなど、さまざまな思いをもって、国立アイヌ民族博物館バーチャル博物館を紹介する映像「National Ainu Museum Virtual Tour」を作成し、ICOMの会員として、AVICOM(オーディオビジュアル及びソーシャルメディア新技術国際委員会) の映画祭に提出した。また、当館館長、佐々木史郎氏の博物館研究者としての人生物語をテーマとした短編映像も同時に提出した。
7月、AVICOMの受賞連絡メールが届いた。どちらの作品がどのような賞を受賞したかということは秘密だった。第26回ICOMプラハ大会の間に開催する受賞式の現場にいくまで、公開されていなかった。受賞式は銅賞、銀賞、金賞の順番に、世界中から選ばれた受賞者の名前が呼ばれ、その優秀作品の一部が上演されてから、次の受賞者が表彰されるという形式であった。時差の倦怠感にくわえ、ほぼ最後までに待たされ、もう我慢できない尿意、もしかして受賞はないのではないかという自己懐疑さえあったが、もっとも新技術を代表するといえるAR・VR部門の金賞に、「National Ainu Museum」の名前を聞いた瞬間、隣に座っていた館長に「まさか!」の驚きが響いた。自分も全く同じ感覚であった。
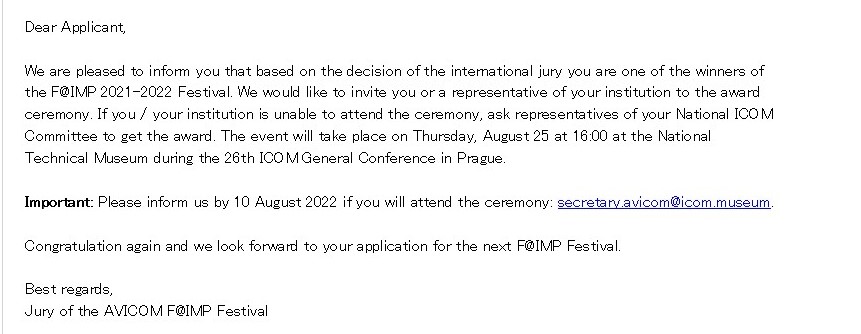
この「バーチャル博物館」が世界中に見られて、嬉しい!
「バーチャル」は、民族学系の博物館展示にとって実際に重大な意義があると筆者は思っている。民具、衣装などの民族資料は、その民族の人々が本当に利用したものであるため、万全な状態で蒐集されたものが少ない。実物展示会のため、借用、運送の作業で、徐々に傷がついていく。だが、新技術によって作られた「バーチャル」展示品は、収蔵品損傷という心配がなく、コンテンツを更新しやすく、労力もかからない。
さらに、絵画、土器などの文化財の展示と違い、民族学の展示では、主題がモノではなく、その民族の人々である。モノを含めて、その民族の文化、生活、過去と未来の情報をなるべく伝えたい。言語学、民族学、人類学の研究者は、研究対象の言語を学び、その民族のコミュニティーに入り込み、長期の参与観察を通じて理解を深める。それに比べて、博物館の来館者には、短時間の見学のうちに、民族の文化の概要を理解してもらわなければならず、それは実物資料を見るだけではとても難しい。そこで、VR、CG技術を運用し、民族学フィールドワークのような仮想世界を体験すれば、単一の実物展示より良い効果があると考えられる。「バーチャル」はそのソフトウェアと柔軟性の高さにより、実物より多くの可能性がある。
文化財が有形と無形にわかれ、両方とも大切であるのと同じように、民族学系の展示も「有形」と「無形」双方を重んじなければならない。民族文化発信のために、その両方を組合せることからさまざまな活動が生まれてくることが期待される。
(りゅう かおり)
[i] Weblio https://ejje.weblio.jp/content/virtual
[ii] 英辞郎 https://eow.alc.co.jp/search?q=virtual
[iii] 日本バーチャルリアリティ学会編(2011)「バーチャルリアリティ学」、pp5-7